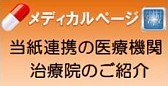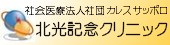サッカーアラカルチョ
一覧に戻るヨーロッパサッカー回廊『ブラジルワールドカップから見えてくるもの』
14・07・17
北米、中・南米以外のフットボールファンはこの一か月時差ボケになったのではないだろうか。
32日にわたるブラジルワールドカップは筆者の予想(5月稿)通りドイツがアルゼンチンを破り、新装したマラカナンスタジアムにジュール・リメ杯を掲げた。
1982年のスペインワールドカップ以来、初めて日本に滞在し、半ば外国人の目でこのW杯を見た印象は「日本っていいなー」、「平和ボケしているなー」、「フットボールがメインのスポーツになったなー」、「お祭りと覇権を争う厳しい大会と同じ目線で見られて幸せだなー」という感想が湧きあがってきます。
まずは大会前、日本代表チームへの期待度が漫画の世界のように膨れ上がっていたこと。少なくとも8強入りは確実、あわよくば4強も夢ではないというメディアの過熱気味報道は、本当に世界のフットボールの現実を知っているのかと疑問を持たないわけにはいかなかった。
しかも選手からも「優勝できる。する。」といったいわば大言壮語的な言葉も見受けられたのには驚いた。そして異口同音に「自分たちのSoccerをすれば勝てる」と、相手があってのフットボールということを忘れ、違うスタイルのフットボールがあることも忘れ、あたかも自分たちのSoccerが存在するかのごとき錯覚を持って臨んでいたようだ。
これは地元ブラジルも似た現象であったようだ。「優勝は当たり前、ブラジルのFootballをすれば無敵である」とか。
このようなゲーム感覚のフットボールは2012年までのスペインに代表される『ティキタカ』で終わっていたのにもかかわらずである。そのことを日本代表は察知できなかったのか、『ティキタカ』を超えるものはないという夢想的なフットボール感に浸っていたつけが回ってきたのが今回の結果と言える。
W杯の予選を勝ち抜くにはどうするか、ここ数年世界王者として君臨したスペインの完成された選手と技術を打ち破るにはどうすべきなのか。世界のフットボール王国、特にヨーロッパの各国はこのW杯に備えて模索し、ある程度の答えを出しつつあった。
それはフットボールの原点である『走る、蹴る、タックルする、頭のスピード感を上げる、そして得点する』という格闘技としてのフットボールの基本に立ち戻ることであったと言えよう。
筆者はW杯を5月の稿で予想したが、その根拠はここ2年のヨーロッパにおけるフットボールの変質と挑戦を見ての予想であった。
立ち後れ組の典型としては、ベスト8に残れなかったイングランド、イタリア、スペイン、ポルトガルが挙げられる。イングランドはプレミアリーグの国際化で、地元選手層が薄くなり世界的と言える選手を生み出せる余地がなく、もはやフットボール大国とは言えなくなってしまったのである。
イタリアも然り、産業としてのセリエ低落から生きの良い若手選手の台頭が希薄となってしまった。スペインも2008年以来2012年まで世界の頂点を極めた、彼らの特徴である『ティキタカ』から脱却できず、ピークの選手の老齢化でその特徴は薄れ、新鮮な選手を生み出せないまま無敵艦隊沈没となってしまったのである。
一方、南米有利と思われた今大会。優勝候補の地元ブラジルもいわゆるブラジル的な技術、個人の力を発揮できず、結局、準決勝でドイツに屈辱的な1−7という敗北を喫したのは、あまりに選手のヨーロッパ化が進み23人中19人がヨーロッパクラブ所属という現実があったからこその結果と思われる。
アルゼンチンも然り。メッシをはじめ19人がヨーロッパクラブ所属であり、1人の天才だけで勝てる程のレベルの大会ではなかったのである(ちなみにW杯選手登録の736人の内、約60%がヨーロッパクラブ所属だった)。
そこにはかっての南米的フットボールは姿を消し、ヨーロッパ化した南米人によるフットボールに変わってしまったのである。
ペレ、マラドーナ時代の1人のスーパースターによるフットボールは姿を消し、組織のフットボールが主流となり、今までのポゼッションフットボールから、機を見ての高速カウンター攻撃のフットボールに変質してきたのである。
それだけにベスト4に残った国はいずれも短距離ランナーとマラソンランナーをそろえていた。代表的なのはオランダのロッベンであろう。スペイン戦で見せた80mもの移動距離を100mに換算し、10秒2で走るスピード競争からターンしシュートを決めたシーンは、勝つためにはスピードのある選手が必要であるという一昔前のフットボールを思い起こされた試合であった。
昔60年代にクラマーさんが日本代表を指導した際「自分がトップスピードになった時こそ、シュートなりパスをすべきだ。但しExactlyに。そうすれば相手は読めない。」といった言葉が思い出される。
ポゼッションフットボール対策とはいえ、相手にボールを持たせて時間を稼ぐのではない。ボールを持った選手へは果敢にチャージし、スライディングタックルし、時には体ごと相手に投げ出し、ボールを取りに行くファイティングフットボールでもある。一時の有余も与えないフットボールである。
ボールに激しく、そしてボールを取るという強い意志を持った選手しか生き残れないフットボールでもある。“ちんたら、よいこらしょ”のぬるま湯的なフットボールはシニアだけでいい。
これらの要素を満遍なく90分、120分と奮闘したのはドイツとオランダであろう(筆者の5月時点での予想はドイツ対オランダの決勝戦であったが)。オランダはアルゼンチンにPKで敗れたが過去のフットボールから脱皮し、戦術家ファンファール監督の采配によって決勝戦に出てもよい国であったと思っている。
だからこそドイツが優勝したのである。低迷期の90年後半から今までやっていなかった学校でのフットボールを復活させ、ユース選手の発掘に重きを置き、2009年のUEFA U21選手権の覇者となり、その中から6人もの選手がアルゼンチンとの決勝に出場しているのは偶然ではない。もちろん勝つため、スペインの『ティキタカ』スタイルの打破も入っている。
ドイツのストライカー、ミュラーが7試合で走った距離はマラソン2レース分の83kmにも及ぶ、考えて走るのではなく、走りながら考える90分、120分なのだ。ストライカーがこれだけ走るフットボールは今まで考えられなかったのではないだろうか。ドイツの優勝は新しいフットボールの原点に回帰したこととして意義は大きい。
さて、このようなヨーロッパの、世界のフットボールの変革の中で今後、日本代表チームがどう世界と対抗していくのであろうか。課題は多い。
Jリーグのレベルアップが不可欠なことは揺るぎない。トップ外国人選手のJへの移籍、審判の質の向上(ジュニアからトップまで)も言うまでもない。
スピード(走力、判断力)のある選手の育成、勝利意欲の高揚、ストライカーとGKの育成、そしてメンタリティに合った代表監督の選定とInternational な日本人コーチの選定(ベスト4の国は自国の監督であった)。国際試合はすべて遠征で武者修行、メディアの意識改革等々上げればきりがないが、これから4年間ですべてやるだけの器量を持ったInternationalな『Football governing body and Management』の出現こそが求められているのではないだろうか。
※International Football governing body and Management(編集部訳→国際的フットボール統括組織の構成、管理者)
◆筆者プロフィル◆
伊藤庸夫(いとうつねお)
東京都生まれ
浦和高校、京都大学、三菱重工(日本リーグ)でプレー、1980年より英国在住
1980−89:日本サッカー協会国際委員(英国在住)
89−04:日本サッカー協会欧州代表
94−96:サンフレッチェ広島強化国際部長
2004−06:びわこ成蹊スポーツ大学教授
08 :JFL評議委員会議長(SAGAWA SHIGA FC GM)
現在:T M ITO Ltd.(UK)代表取締役
32日にわたるブラジルワールドカップは筆者の予想(5月稿)通りドイツがアルゼンチンを破り、新装したマラカナンスタジアムにジュール・リメ杯を掲げた。
1982年のスペインワールドカップ以来、初めて日本に滞在し、半ば外国人の目でこのW杯を見た印象は「日本っていいなー」、「平和ボケしているなー」、「フットボールがメインのスポーツになったなー」、「お祭りと覇権を争う厳しい大会と同じ目線で見られて幸せだなー」という感想が湧きあがってきます。
まずは大会前、日本代表チームへの期待度が漫画の世界のように膨れ上がっていたこと。少なくとも8強入りは確実、あわよくば4強も夢ではないというメディアの過熱気味報道は、本当に世界のフットボールの現実を知っているのかと疑問を持たないわけにはいかなかった。
しかも選手からも「優勝できる。する。」といったいわば大言壮語的な言葉も見受けられたのには驚いた。そして異口同音に「自分たちのSoccerをすれば勝てる」と、相手があってのフットボールということを忘れ、違うスタイルのフットボールがあることも忘れ、あたかも自分たちのSoccerが存在するかのごとき錯覚を持って臨んでいたようだ。
これは地元ブラジルも似た現象であったようだ。「優勝は当たり前、ブラジルのFootballをすれば無敵である」とか。
このようなゲーム感覚のフットボールは2012年までのスペインに代表される『ティキタカ』で終わっていたのにもかかわらずである。そのことを日本代表は察知できなかったのか、『ティキタカ』を超えるものはないという夢想的なフットボール感に浸っていたつけが回ってきたのが今回の結果と言える。
W杯の予選を勝ち抜くにはどうするか、ここ数年世界王者として君臨したスペインの完成された選手と技術を打ち破るにはどうすべきなのか。世界のフットボール王国、特にヨーロッパの各国はこのW杯に備えて模索し、ある程度の答えを出しつつあった。
それはフットボールの原点である『走る、蹴る、タックルする、頭のスピード感を上げる、そして得点する』という格闘技としてのフットボールの基本に立ち戻ることであったと言えよう。
筆者はW杯を5月の稿で予想したが、その根拠はここ2年のヨーロッパにおけるフットボールの変質と挑戦を見ての予想であった。
立ち後れ組の典型としては、ベスト8に残れなかったイングランド、イタリア、スペイン、ポルトガルが挙げられる。イングランドはプレミアリーグの国際化で、地元選手層が薄くなり世界的と言える選手を生み出せる余地がなく、もはやフットボール大国とは言えなくなってしまったのである。
イタリアも然り、産業としてのセリエ低落から生きの良い若手選手の台頭が希薄となってしまった。スペインも2008年以来2012年まで世界の頂点を極めた、彼らの特徴である『ティキタカ』から脱却できず、ピークの選手の老齢化でその特徴は薄れ、新鮮な選手を生み出せないまま無敵艦隊沈没となってしまったのである。
一方、南米有利と思われた今大会。優勝候補の地元ブラジルもいわゆるブラジル的な技術、個人の力を発揮できず、結局、準決勝でドイツに屈辱的な1−7という敗北を喫したのは、あまりに選手のヨーロッパ化が進み23人中19人がヨーロッパクラブ所属という現実があったからこその結果と思われる。
アルゼンチンも然り。メッシをはじめ19人がヨーロッパクラブ所属であり、1人の天才だけで勝てる程のレベルの大会ではなかったのである(ちなみにW杯選手登録の736人の内、約60%がヨーロッパクラブ所属だった)。
そこにはかっての南米的フットボールは姿を消し、ヨーロッパ化した南米人によるフットボールに変わってしまったのである。
ペレ、マラドーナ時代の1人のスーパースターによるフットボールは姿を消し、組織のフットボールが主流となり、今までのポゼッションフットボールから、機を見ての高速カウンター攻撃のフットボールに変質してきたのである。
それだけにベスト4に残った国はいずれも短距離ランナーとマラソンランナーをそろえていた。代表的なのはオランダのロッベンであろう。スペイン戦で見せた80mもの移動距離を100mに換算し、10秒2で走るスピード競争からターンしシュートを決めたシーンは、勝つためにはスピードのある選手が必要であるという一昔前のフットボールを思い起こされた試合であった。
昔60年代にクラマーさんが日本代表を指導した際「自分がトップスピードになった時こそ、シュートなりパスをすべきだ。但しExactlyに。そうすれば相手は読めない。」といった言葉が思い出される。
ポゼッションフットボール対策とはいえ、相手にボールを持たせて時間を稼ぐのではない。ボールを持った選手へは果敢にチャージし、スライディングタックルし、時には体ごと相手に投げ出し、ボールを取りに行くファイティングフットボールでもある。一時の有余も与えないフットボールである。
ボールに激しく、そしてボールを取るという強い意志を持った選手しか生き残れないフットボールでもある。“ちんたら、よいこらしょ”のぬるま湯的なフットボールはシニアだけでいい。
これらの要素を満遍なく90分、120分と奮闘したのはドイツとオランダであろう(筆者の5月時点での予想はドイツ対オランダの決勝戦であったが)。オランダはアルゼンチンにPKで敗れたが過去のフットボールから脱皮し、戦術家ファンファール監督の采配によって決勝戦に出てもよい国であったと思っている。
だからこそドイツが優勝したのである。低迷期の90年後半から今までやっていなかった学校でのフットボールを復活させ、ユース選手の発掘に重きを置き、2009年のUEFA U21選手権の覇者となり、その中から6人もの選手がアルゼンチンとの決勝に出場しているのは偶然ではない。もちろん勝つため、スペインの『ティキタカ』スタイルの打破も入っている。
ドイツのストライカー、ミュラーが7試合で走った距離はマラソン2レース分の83kmにも及ぶ、考えて走るのではなく、走りながら考える90分、120分なのだ。ストライカーがこれだけ走るフットボールは今まで考えられなかったのではないだろうか。ドイツの優勝は新しいフットボールの原点に回帰したこととして意義は大きい。
さて、このようなヨーロッパの、世界のフットボールの変革の中で今後、日本代表チームがどう世界と対抗していくのであろうか。課題は多い。
Jリーグのレベルアップが不可欠なことは揺るぎない。トップ外国人選手のJへの移籍、審判の質の向上(ジュニアからトップまで)も言うまでもない。
スピード(走力、判断力)のある選手の育成、勝利意欲の高揚、ストライカーとGKの育成、そしてメンタリティに合った代表監督の選定とInternational な日本人コーチの選定(ベスト4の国は自国の監督であった)。国際試合はすべて遠征で武者修行、メディアの意識改革等々上げればきりがないが、これから4年間ですべてやるだけの器量を持ったInternationalな『Football governing body and Management』の出現こそが求められているのではないだろうか。
※International Football governing body and Management(編集部訳→国際的フットボール統括組織の構成、管理者)
◆筆者プロフィル◆
伊藤庸夫(いとうつねお)
東京都生まれ
浦和高校、京都大学、三菱重工(日本リーグ)でプレー、1980年より英国在住
1980−89:日本サッカー協会国際委員(英国在住)
89−04:日本サッカー協会欧州代表
94−96:サンフレッチェ広島強化国際部長
2004−06:びわこ成蹊スポーツ大学教授
08 :JFL評議委員会議長(SAGAWA SHIGA FC GM)
現在:T M ITO Ltd.(UK)代表取締役
伊藤 庸夫